-
印象派を代表する画家のひとり、マネによる有名な絵画『草上の昼食』です。当時大スキャンダルを起こしたこの絵画、いったい何がショッキングなのでしょうか。そして、マネはいったいこの絵で何を目指したのでしょうか。
まず、絵を見てみましょう。

人々が森でピクニックをしています。男性が服を着ているのに対して、女性は服を着ていません。男性たちは、スーツにネクタイという正装をしているため、より一層女性のヌードが引き立っています。
画面左下には彼女が脱いだと思われるドレスと麦わら帽子が見えます。

ということは、彼女はこの森に来てから服を脱いだことになります。でも、いったいなぜ?この理由がわからない。いろいろな推論を立てても、この絵自身によって否定される、そのような構造にこの絵はなっています。
例えば、こう考えてみましょう。
画面奥には水辺があり、水浴をしている女性がいます。この奥の女性が水浴をしているように、手前の女性も水浴をしていたのだ、と。

しかし、それは変です。画面奥で水浴をしている女性は肌着を着ているけども、水浴をしていない女性は、裸です。本来であれば、水浴をしているほうが裸であるのが自然ですね。
実は、19世紀の慣習に忠実なのは、この服を着たまま水浴する女性のほうなのです。当時、女性はあまり肌を見せる習慣はなく、水浴をするときでも、水着の上にこのような肌着を着るのが普通でした。人前で裸を見せるのは、娼婦ぐらいでしたが、娼婦でも森の中で裸を見せるような時代ではありません。手前の女性が水浴をしていたとしても、肌着まで脱いでしまっているのはおかしいのではないか、と疑問が残ってしまうのです。
それでは、今度はこう考えてみましょう。
彼女は生身の人間ではなく、音楽の妖精、芸術の精霊 (ムーサ)のような存在であり、男たちには見えておらず、この世の存在ではないのだ、と。
実は、この絵にはモデルがあります。16世紀にヴェネツィアで活躍したティツィアーノが描いた『田園の奏楽』という絵画です。ルーブルのモナリザが展示されている壁のちょうど反対側に展示されています。

構図が似ていますね。木陰に服を着た男性が2人座っていて、手前には裸の女性が二人います。この絵画が非常に奇妙に見えるのは、若い男性が目の前にいる裸の女性に全く注意を払っていないことです。裸の女性が目の前にいれば、見てしまうのが男というもの。若い男ならばなおさら、とおもいますが。。。彼らがこの裸婦を注視していないのには、理由があります。彼らには彼女達が見えないのです。
ヴィロードのような光沢のある赤色の服を着ている男性はリュートを奏で、質素な服をきている男性はその音色に合わせて唄を歌っているのでしょう。その美しい音色に誘われて、いま音楽の精霊が舞い降りてきた、という主題をこの絵画は表現しているのです。笛を持っているのは音楽と抒情詩の精霊。もう一人の女性が、水差しをもって泉のそばに立っているのは、泉から水が湧くように、彼女たちのおかげでアーティストたちは芸術的なアイディアが湧いている、ということを意味しています。
では、マネに戻ります。この女性を芸術の精霊ということができるか。できません。男たちはいかなる芸術的な行為を行っていない上に、決定的なのは、この女性が脱いだであろう服が前に見えているからです。服を着て、麦わら帽子をかぶってやってきて、男たちの前で服を脱いだ。そんな精霊いるはずがありません。
この絵が面白いのは、鑑賞者がなんとかして裸である女性の理由を考えたとしても、この絵自身によってその仮定が反駁されてしまうことです。
なぜ裸の女性が森の中にいるのかがわからない。この絵が鑑賞者に強い非難を受けたのは、まさにその理由からでした。
考えられるとしたら、「脱ぎたかったから脱いだのだ」ということになります。水浴をする時でさえ、肌着をつける時代に、何の理由もなく、自分の部屋でもない場所で裸になるとは何事か。そんな女性を大画面にでかでかと描き、それを芸術と称するマネという男は、芸術を馬鹿にしている。そう当時の人は考えたのです。
さらに、鑑賞者の気に障ったのが裸の女性の視線です。女性はこちら側をじっと見ています。

この女性の態度も、この絵が批判された理由の一つでした。というのも19世紀では女性が正面から相手の目を見ることは、無礼だと考えられていたからです。この絵画完成の数か月後、『オランピア』のなかで同じような女性の直視を使います。下の絵がオルセー美術館所蔵の『オランピア』。彼女もまた、私達のほうをじっと見ています。

マネが確信犯だと思われても仕方ありません。
『草上の昼食』の裸の女性の描写にも問題がありました。裸体が、リアルすぎるのです。当時は、女性の裸体を表現する際は、理想化するのが原則でした。すべてが忠実に写り込んでしまう写真ではないのですから、美しくない部分、例えばムダ毛、贅肉、ほくろなどは絵画のなかでは削除してしまうのが常識です。
そのような時代の中で、マネは非常に写実的な身体を描いています。お腹の部分には、たるんだ贅肉が。ももの後ろも皮下脂肪が忠実に表現されています。古典主義の作家たちが、身体を理想化したのとは反対に、マネは彼女がもっている「美しくない」部分も描きました。
裸婦を描く上でのルールを守っていない上に、下品。それがこの絵に下された評価でした。
しかし、マネは絵画伝統を馬鹿にしているわけでも、ただ単にスキャンダルと起こそうとしているわけではありませんでした。では、いったい彼は何がしたかったのでしょうか。
もう一度、絵に戻ります。

この絵は見れば見るほど奇妙な絵です。全く自然でなく、むしろ人工的なのです。
まず、光に注目してください。この前景にいる3人に強い光が当たっていますが、木陰にいるはずのかれらには、このような人工的ともいえる光は当たらないはずです。ここからわかるのは、マネはこのシーンを描くために、実際の森にピクニックへいき、そこでこの絵を描いたのではない、ということです。
今度は人物たちのポーズをみてください。

彼女の右ひじは膝の上に乗っていません。ということは、何の支えもなく宙に浮かしているということです。実際の場面ではそんな疲れる体勢は誰も取りませんね。裸の女性はあきらからに画家のアトリエでポーズをとっているということです。
前面にいる人物たちは、互いに触れ合っていません。そして、互いに目線が合うなどのしぐさも見られません。右のターバンを巻いた男は、二人に話しかけているようなしぐさをしていますが、左の人物は誰一人それにこたえていません。
この人物たちのポーズは、16世紀の巨匠ラファエロの絵をもとにした版画から来ていることがわかります。(下の絵:ラファエロ作、『パリスの審判』の版画には、『草上の昼食』と同じポーズの人々がいる)

ターバンの男性と、裸の女性はほとんど同じポーズですね。
マネは、古典作品の構図、人物のポーズを土台にして、その人物を理想化した姿ではなく、彼らが誰かと特定できるほどの正確さで表現しました。つまり、古典作品を現代風にアレンジする。これが、マネの目指したことでした。
ティツィアーノの寓話画を19世紀当時のピクニックという主題に変形させ、人物のルネサンス時代の服装を19世紀のものに、そして、音楽の妖精の姿を、当時の生々しい本物の女性に変化させました。
芸術とは、その時代の現実に根差していなければいけない、というのがマネの主張であり、目の前にある生々しい理想化されていない裸体こそ、マネのいう「現実」なのです。
マネは過去の美術史と関係を断ち切るのではなく、あくまで過去の遺産の上に新しい19世紀のリアルを取り入れようとしました。実際、マネはティツィアーノ、ラファエロを称賛していました。
マネの絵を批判し、非難した人々は、このような彼の美術史的な観点を持っていなかったので、スキャンダラスな面のみが強調されてしまったのです。
このようにして、美術史のなかの「裸体」というテーマに、彼は新しい1ページを付け加えたといえます。
題名 『草上の昼食』 (作者31歳の時)
年号/素材 1863 キャンパスに油彩
作者/エドワール・マネ(1832-1883)
オルセー美術館の5階、印象派スペースに展示
解説があると、絵画鑑賞はもっと面白いですね。
(中村)
[みゅう]パリ 美術コラム 『草上の昼食』エドワール・マネ
2016-05-23
最新記事



 お問い合わせ
お問い合わせ マイページ
マイページ カート
カート よくある質問
よくある質問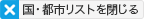



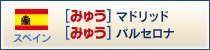


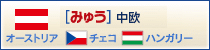

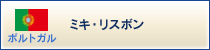
 [みゅう]プライベートルーブルツアーの集合場所が工事中
[みゅう]プライベートルーブルツアーの集合場所が工事中  2025 ブルゴーニュのサンヴァンサン祭り ~コルトンワイン
2025 ブルゴーニュのサンヴァンサン祭り ~コルトンワイン  フランスのワイン祭り~ボーヌ栄光の3日間
フランスのワイン祭り~ボーヌ栄光の3日間  参加してきました!大人気[みゅう]バスで行く 日帰りモンサンミッシェル オムレツの昼 ...
参加してきました!大人気[みゅう]バスで行く 日帰りモンサンミッシェル オムレツの昼 ...  見どころいっぱい!芸術家が愛した地 パリのモンマルトル
見どころいっぱい!芸術家が愛した地 パリのモンマルトル  パリで開幕!!!!!
パリで開幕!!!!!